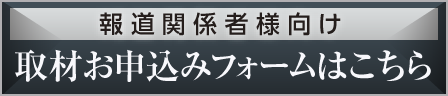アルコールや薬物などの依存性を持つ物質(依存性物質)を摂取する習慣が、その習慣によって明らかに健康を害する問題や苦痛を生じていながらも継続されている状態。乱用、依存、病的依存などの用語は、使用する人たちによって定義がばらついており、線引きは難しい。
アメリカ精神医学会による精神障害の統計・分類基準DSM-Ⅳ、WHOの国際疾病分類基準ICD-10に掲載された問題水準のギャンブリング習慣に対する診断分類の基準。DSM-5への改定によりDSMからは病的賭博はなくなった。また近く改定されるICD-11からもなくなる予定である。DSM-5のギャンブリング障害とは異なる基準であり、ギャンブリング障害の中等度の一部から重度のレベルが病的賭博に相当すると推測されている。診断においては、医師等の専門による確定が必要。いわゆる従来のアルコールなどの「依存症」と同じような水準と読み替えられ、「ギャンブリング依存症」と恣意的に書き換えられることが多く、用語混乱の一因となってきた。...
依存問題領域における相互援助(自助)グループは、問題を抱えた当事者(本人、家族等)が自発的に定期的に集まり体験の共有を行うミーティングの形式で、日本では言いっ放し、聞きっ放しのスタイルが主となっている。ギャンブリングへののめり込みでは、本人のグループGA(ギャンブラーズ アノニマス)、家族のグループ(ギャマノン)が、日本各地でミーティングを開催している。...
問題を抱える人やそれらの問題に関わることで悩みや苦痛を抱える人たちに対して専門家が電話や対面で話を聞き、問題解決の支援を行うこと。
問題を抱える人やそれらの問題に関わることで悩みや苦痛を抱える人たち
何らかの理由で社会との関りが上手くいかなくなり、社会との関係が中断している人たちが、再び社会との関係性を築き直し暮らしていくこと。
精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に定められた精神障害者の福祉の増進を図るために設置された公的な機関。都道府県単位、または政令指定都市に設置されている。都道府県によっては名称が精神医療センターとなっているところもある。業務内容は地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助など広範囲にわたっている。特定相談事業として、アルコール、薬物、思春期、認知症の相談を実施。国のギャンブル等依存症対策の一環として、全国の精神保健福祉センターにギャンブル等依存問題に対応する相談員67名が配置が決まっている。...
精神の疾患の原因解明、治療などについての研究や診療を行う医学的分野。精神疾患や精神障害の概念の変化、広がりによって、精神医学の領域は医学領域を超え他の自然科学、工学、経済学、宗教などど癒合しつつある。
人間の思考や感情などは脳内の活動によって作り出されている。脳は、神経細胞が集合してできており、神経細胞と神経細胞の情報のやり取りは、様々な脳内に存在する神経伝達物質と呼ばれる脳内物質の濃度や細胞との反応によって行われている。様々な原因で脳内物質のバランスが崩れると、精神活動が円滑に行われなくなる。アディクション・依存の形成にも、脳内物質が深く関与していることが知られている。ドパミンやセロトニンなどは、脳内物質として重要な役割を果たしている。...
ギャンブリング参加者が、自らギャンブリングの遊び方に関する制限(時間や使用金額など)をギャンブリング提供者に申告し、その申告に基づいてギャンブリング提供者がプレーヤーの遊び方の制限を支援するプログラム。ギャンブリング参加自体を排除するものではなく、自発的な自己制限プログラム。